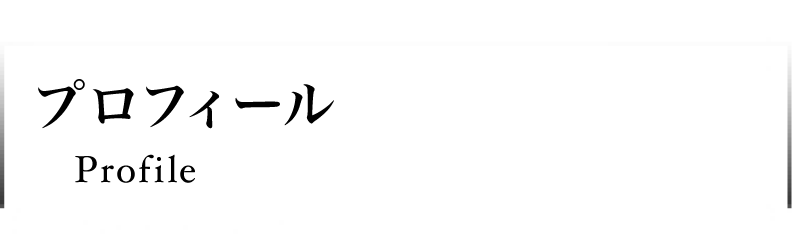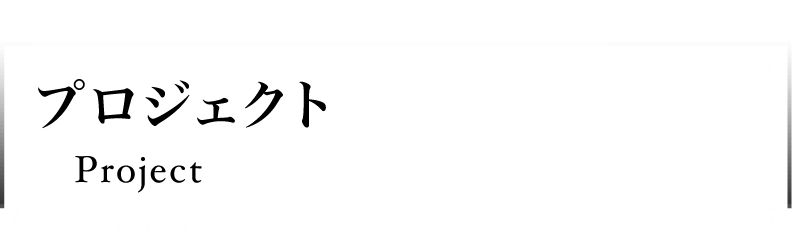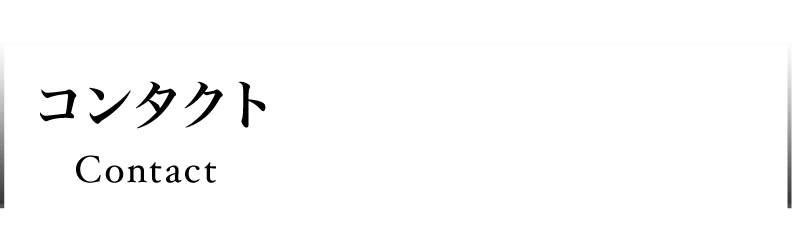劇作家キム・ヒジンさんからのインタビュー
話し手:酒井一途
聴き手:キム・ヒジンさん(劇作家、演出家、劇団膝主宰)
・自己紹介をお願いします。
作り手として演劇に関わってきながら、作品を上演することよりも、作品づくりのプロセスに価値があることを感じてきました。プロセスにおいてこそ変化が生じる。「こうしたい」という意思が多様に入り乱れ、たがいに対話を深めて他者を知りながら、よりよい方向に向かっていくためのプロセス。オーディエンスもまた、完成した作品を観るだけでなく、そのプロセスに参加してくることが、アートにおける有機的な関係性をつくると思います。創作やアートに限らず、多くのことが「参加」に関わります。地域も、まちづくりも、政治も。そのような「プロセスへの参加の場」をつくることを、作品をつくることそのものからは一旦遠ざかりながら、広く探究しています。
・どのようなアプローチで創作をしていますか?
人が本音でその場にいることのできる場をつくることを大事にしています。自由であることのできる場。生きていると、人はその立場に応じた役割や振る舞いを演じることが求められます。社会においても家庭においてもです。共同体が成り立つ上でそれは必要なことですが、自分の本音に真正面から向き合って解放することのできる場を知らずにいると、無意識に自分を抑圧して心身を害する可能性がある。社会的な役割や立場、自らの属性から解放され、自由自在でいられる場を日常の中に組み込むことで、その「余白」の時間がそれ以外の自分の人生の時間に対して、余裕を生むのではないでしょうか。ですから余白の場、時間をつくるということがアプローチの仕方です。
・演劇を始めたキッカケはなんですか?
母がすごく陽気で目立つひとなんです。息子である僕の姿からは想像つかないくらい笑。子どもの頃はその母とよく一緒にミュージカルの舞台を観に行っていて、舞台の上で輝いている俳優たちをみながら、母に対する憧れと重なって見えてくるように感じました。人びとの中心で輝いて、周りのひとたちのことも明るく照らすような存在になりたいと思ったのが、演劇に惹かれたきっかけです。高校に入ってから演劇を始め、役者をしたり、また脚本を書いて演出したりしながら、創作活動を始めることになりました。
・最近興味を持っていることはなんですか?
2020年春、生まれ育った東京を離れ、兵庫県の日本海側に位置する豊岡という地に移り住みました。この地で「内と外をつなぐ」ことを実践していきたいと思っています。地域と外、アートと外、作り手とオーディエンス。意識するから境界が生じる、とも言えますが実際のところ「内と外」のハブとなる媒介者は必要です。こうした仕事をすることがこれまでにお伝えしてきたような創作の仕方や、場づくりにゆくゆく役立ってくると思っています。
・豊岡での生活はどうですか?
心を開放的に、ゆたかな日々を送っています。東京にいた頃は、人や情報の多さに自分の感覚を閉ざさざるをえないことに息が詰まりました。いくつものコミュニティに所属できて、多様さにあふれた都市部での生活は刺激的で楽しいですが、生活に結びつくコミュニティがないことに気づきました。住んでいる地域にほかに誰が暮らしているのかも知らない。地域での生活には都市部とはまたべつの多様性があります。行きつけになった活魚料理の料理長、図書室的なスペースを運営する医者、海辺に住む漁師、中古車販売の店主。これまで都市部の生活では出会えなかったジャンルの人たちと生活に結びつきながら人間関係を築けるという魅力があります。
・豊岡演劇祭での活動を教えてください。
豊岡演劇祭は、2020年から始まった国際演劇祭です。自主参加型の公演を受け入れて見本市的な機能を持たせる「フリンジ型」演劇祭として発展させていくという構想があります。初年度も主催公演9団体とフリンジ団体23団体が上演を行い、コロナ禍の客席数半数以下等の対策の上で5000人の動員を果たしました。そのなかで僕はフリンジコーディネーターとして、地域とアーティストを結ぶ役割として動いています。滞在制作のサポートやリサーチのための人の紹介やアテンドなど、性に合っている仕事のようです。
・今までのお仕事の中で印象に残っているエピソードはありますか?
2019年2月に目黒にある高野山真言宗高福院というお寺からお声がけいただき、『共感と自由 演劇の身体知による実践』というワークショップをしたときのことです。20代から50代以上まで、会社役員や経営者、会社員、精神科の看護師、翻訳と通訳のフリーランス、不動産賃貸の代表取締役、経営コンサルタント、福祉系の相談員など様々な肩書きの参加者が集いました。終わった後のアンケートで、「相手をちゃんと丁寧に見て、自分の好きなとこを素直に伝えるだけでも、相手との関係を変えられると実感した」「人に対してこの短い時間でこれほど『好き』と言ったことがなかった。人の良いところを見つけようとする姿勢が相手にも伝わる」といった感想をいただき、じぶんがこれから作っていきたい理想の場をワークショップで体現できたと思えた時間でした。
・芸術の魅力を教えてください。
たとえば道端に咲いている野の花をみたとき、多くのひとは気づきもしないまま歩き去ってしまいます。けれど、誰かがその花に目をとめて愛ではじめたとき、その花はその誰かにとって特別なものになります。ただやはり依然として、ほかの誰かにはこのことは説明しづらいのです。通り過ぎていくひとに「僕はこの野の花がほんとうに美しいと思うんだ」と語りかけたところで、「ふーん」と言って立ち去られてしまうでしょう。藝術はその美しい花を特別なものとして、ほかのひとの目にも気づかせるものだと思います。
・影響を受けたアーティストや作品はありますか?
詩人のライナー・マリア・リルケが好きです。人間が生きているあいだにできることとして、人間は言葉をもつから、言葉をもたないこの世界のほかのものたちに、言葉をみいだすことができます。目にとまった特別なものたちを、言葉で愛しむことができる。野の花に言葉をみいだしたとき、その花はただの花ではない光を放ちはじめる。リルケが直接そういうことを書いているわけではなく、あくまで僕の理解ですが、リルケの詩を読んでいるとそういうことを感じます。生きていることの喜び、死にゆくものへの眼差し、もう死んでいったものたちへの愛が、リルケの言葉からは感じられます。
・酒井さんが思う「人が自由になれる場」とはどんなイメージですか?
愛、愛しむこと、に結びついています。ちょうど今読んでいる本で、パウロ・コエーリョ『11分間』から引用します。「本当に自由な経験とはこういうことだ。この世で一番大事なものを所有することなく、抱きとめること」。愛が束縛することだったり、所有することではなくなったときに、ひとは自由になれる。僕がイメージする場は、そのような自由である場です。
・アーティストとしての人生を振り返ってみると?
自分を手放すということを意識してきました。昔から自意識が強かったんです。周りにどうみられているかを気にしすぎて、でもそのことへの窮屈さも感じていて、どうやって自意識に向き合っていこうかと考えてきた。自意識を殺そうとすると、逆に心に抵抗が生じて苦しくなってしまう。だから自分を殺すのではなく、そういう自分がいることを認めた上で手放していこうと思い始めました。自意識を持たねばならなかった自分の姿を抱きとめる。それによって自分を手放していく。自分を手放した先に、透明な存在になり、美しい世界をそのままに映していくということをしたいと思っています。
・コロナ時代の芸術について
コロナ禍のような危機的な状況において、目の前に起きていることを見つめることはもちろん大事ですが、一方で普遍的なところのものを見つめながら作品づくりをすることだってできます。コロナ禍だからこういう作品をつくるというよりも、コロナ禍でも人間の本質はこういうところにある、ということに関心がある。たとえば海をイメージしてみたとき。嵐が吹き荒れて、雷や大荒れの波があっても、海の底ではずっと静かなままの状態の海があります。僕は、その深い海のほうの世界を見つめたいと思っています。
・今後の夢や目標はなんですか?
これまでに話してきたような「自由のための場」や、「愛しみあう」という世界観をどうやって示し出していけるかということが夢であり、目標でもあります。自分でそのような生き方を実践することはもちろん、ワークショップや作品のプロセスへの参加をしてもらうなかで、関わるひとたちといっしょに愛しむ場をつくっていきます。
"ひとが愛しみあえる、自由のための場をつくりたい" 酒井一途
あらゆるひとが社会的役割や立場、自らの属性、共同体の規範から解放される〈自由のための場〉をつくること。目の前のひとと向き合い、一対一の関係性をみつめる〈演じない〉ためのワークショップをすること。