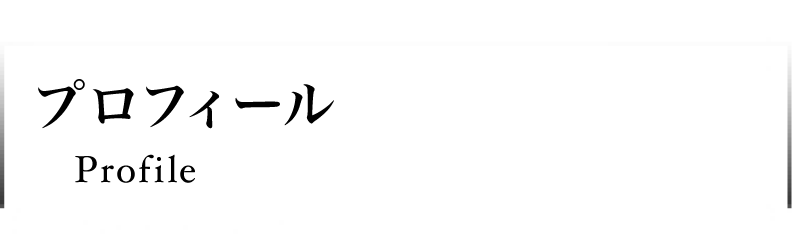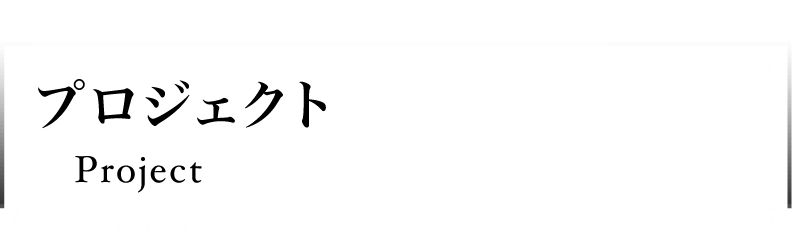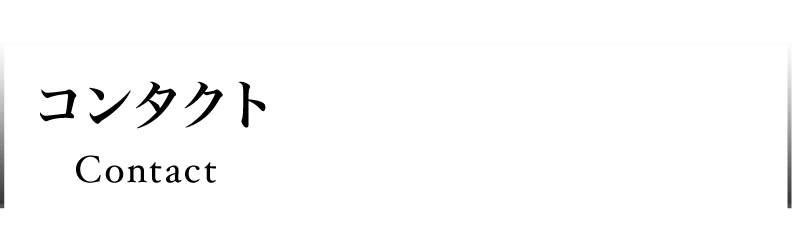レッドトーチ・シアター『三人姉妹』(ティモフェイ・クリャービン演出)感想
2019年10月18日 東京芸術劇場プレイハウスにて観劇
手話でチェーホフ『三人姉妹』の全編が演じられると聞いて、気になったのが、作品のクライマックスにあたる有名なセリフである。
マーシャ まあ、あの楽隊のおと! あの人たちは立って行く。一人はもうすっかり、永遠に逝ってしまったし、わたしたちだけここに残って、またわたしたちの生活をはじめるのだわ
オーリガ 楽隊は、あんなに楽しそうに、力づよく鳴っている。あれを聞いていると、生きて行きたいと思うわ!(神西清訳)
耳の聴こえない彼女たち、三人姉妹が、楽隊の去っていく音をどうやって聴きとるのか。友である軍人たちが、軍楽隊の奏でる音楽と共にべつの地へと去っていく、姉妹たちとの物語を携えながら、おそらくはもう二度と会うことのできない別離である。残される彼女たち、オーリガの、マーシャの、イリーナの生活は、人生は、それでも続いていく。思い描いた夢が遠ざかり、現実の迫ってくることを象徴するこのクライマックスの、物理的な「音の遠のき」を、どのように演出するのか。
答えは、実に誠実だった。「想像」で聴いたのだ。三人姉妹は、たしかに音楽を聴いた。リズムに合わせて手に手を取って高らかに行進までしながら。聴こえるはずのない音楽を、体全身で聴きとって、たがいに笑いあい、感情のすべてを手話に託して、力づよくセリフを手話しつづけた。失意と絶望の果てに、悲劇的なロマンチシズムに陥ることもなく、「生きて行く」ことを宣言するかのような姿だった。
舞台効果としての音楽は、実際に鳴っていた。舞台上では、セリフとして「言葉」が発せられないだけで、すべての音は実際に鳴る。軍楽隊の行進曲も、観客の耳には聴こえていた。ただ、彼女たちには聴こえていないことがわかっていた。クライマックスに至るまで、出演者たちはみな「音」に対して無反応であったから。舞台の人物たちには、聴こえない音楽。観客にだけ、聴こえている音楽。そういう設定のもとで、「聴こえない音楽を聴く」という感動を共感し得た。それまでの丁寧な演出、四時間にわたる上演時間を経てその最後にこそ成しえたことだった。
思えば、作品の冒頭の演出も音楽から始まった。マイリー・サイラスが2013年にリリースした"Wrecking Ball"のMVにあわせて、イリーナが踊るところからこの劇は始まったのだ。大音量で流れる音楽は、観客の耳には当然聴こえ、イリーナにも、あたかも聴こえているかのような始まりだった。なぜなら彼女は自然に音楽に身を任せるみたいに踊っていたから。「聴こえてくる音楽を聴いている」と錯覚して、観客は冒頭のイリーナの姿を見ていた。そして、それは間違っていた。
「聴こえない音楽を聴く」ことと、「聴こえる音楽を聴く」こととは、絶対的にことなる行為だ。演劇が想像力によって「みえないものをみる」芸術であることはよく言われるが、多くのリアリズム演劇において、観客はなにを「みえない」ものとし、なにを「みえる」ものとしているだろうか。そこにはどのような想像力がはたらいているだろうか。ただ舞台に起こることをみさせられる「みえるものをみる」だけの演劇では、退屈が観客を襲う。わたしたちは、演劇というつくられた世界のなかで、現実以上の世界をみなければ、わざわざ演劇を観る理由がない。しかしクリャービン演出の『三人姉妹』では、全編手話という設定のもと徹底的なリアリズムを貫くことによって、「聴こえない音楽を聴く」という想像力が立ち上がった。そして、その想像を観客にまで感じさせることに成功した稀有な作品であった。
* * *
終幕近くなって、イリーナは言う。「あたし生まれてから、一度も愛を味わったことがないの。ああ、あたしどんなに愛にあこがれたことか!」
イリーナと結婚を約束した軍人トゥーゼンバフが、決闘に赴くにあたってそのことは告げないまま、ただイリーナになにかひとことを求めて、その言葉がなにを求めてかはみずからもわからないままに、交わした最後の対話であった。トゥーゼンバフは五年にわたってイリーナに恋し、ついに結ばれることになりながらも、イリーナが自分を愛していないことを知っていた。そしてイリーナは愛を求め、目の前にその愛がありながらも、愛をみずからのうちに最後までみいだせなかった。
彼女が冒頭に聴いていたマイリー・サイラスの歌詞には、「I never hit so hard in love(こんなにも激しく愛したことなんてなかった)」とあった。そしてまた、「I can’t live a lie, running for my life. I will always want you(嘘に生きることはできない、自分の人生のためにわたしは逃げるの。いつでもあなたを求めつづけてる)」とも。
イリーナがこの歌詞をあこがれの思いで聴いていたのか、それともやがて迎え来る悲劇の予兆として聴いていたのかはわからない。あるいはアンビバレントなイリーナに対するシニカルな演出なのかもしれないが、そうだとは思いたくない。
トゥーゼンバフは決闘に死んでいき、二人で共に家を出て暮らしていこうという理想の計画は打ち砕かれた。それでいてなおイリーナは一人で立つことを決意する。「自分の一生を、もしかしてあたしでも、役に立てるかもしれない人たちのために、捧げるわ」と言って。そして姉妹同士で抱き合いながら、去っていく軍人たちと楽隊の音楽を見送った。激しく手話でセリフを続けつつ、聴こえない音楽を聴いて笑うその姿は、晴れやかな絶望のようにもみえた。しかし生に対する希望を彼女は見失ってはいないのだ。生きて行くことの、力づよい宣言をしたのだから。
そうしてみると、これまでにこの戯曲を読んだり、観たりしてきたものとはことなる角度から、イリーナの最後のセリフが聴こえてきた。つまり、多くの愛が不可能なものとして描かれるチェーホフの戯曲において、イリーナのうちにはじめて他者への愛、恋愛の感情ではない「行為としての愛」が芽生えることを示す、兆しのセリフとして。トゥーゼンバフの死によって、もしかしたらイリーナのうちにひとつの想像が生れたのかもしれない。嘘に生きることをせず、愛にあこがれてきたイリーナ。彼女はあたらしい生活にひとりで向かい、「みることのできる愛」ではない形の、「みえることのない愛」をこれからは求めていくのだろう。
絶望をみつつ、なお、「生きて行く」ことの決意を秘めた、希望の劇だった。
* * *
レッドトーチ・シアターは、ロシア・シベリアの中心都市ノヴォシビルスクにある州立劇場。演出家のティモフェイ・クリャービンは、2015年、31歳からこの劇場の芸術監督を務めている。『三人姉妹』は2015年初演、ロシアの国立演劇賞であるゴールデンマスク賞を受賞した。