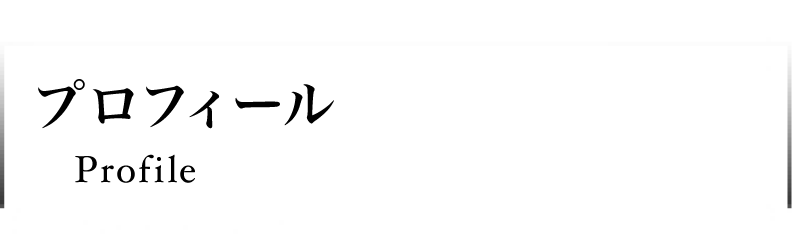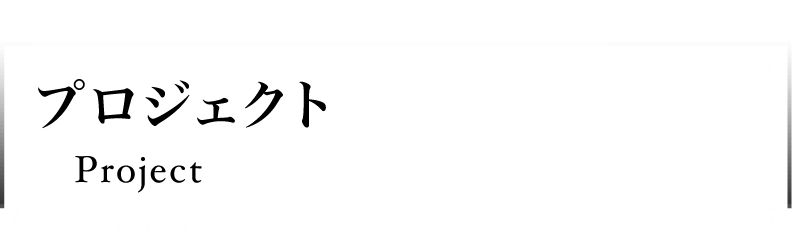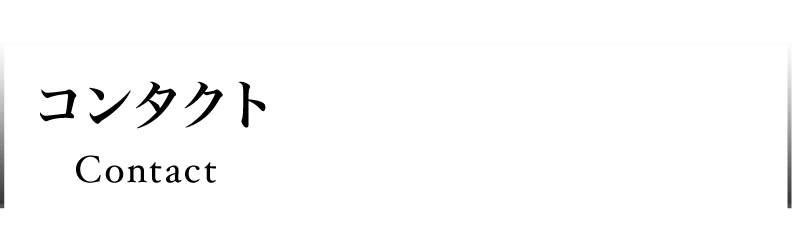自分を丸投げにすること ― 吉増剛造さんによる現代詩シンポジウム/立命館大学
2016年7月6日
京都に来ている。今日は立命館大学に行った。
白詰草の花が一面に咲き誇る美しい庭をもつキャンパスだった。
現代詩を代表する詩人吉増剛造さんの選集が今度英訳の上で新しく出版される、その選集の訳者たちと吉増さんご本人が集い、シンポジウムと朗読が行われるということで、その場に赴いたのだった。
訳者の一人吉田恭子さんは吉増さんの詩を英訳するにあたって、幾度か吉増さんに直接電話で相談をしたという。
吉増さんは電話をかけると必ず出られる、すぐ出られる。だから念入りに念入りに準備して、ドアをノックするくらいの気持で緊張してかける。彼が電話にでる。すると「なんでも訊いてください」と言われる。なんでも。「私はこの声を聴いて、とにかくこのまま読んでいっていいのだと、答えはここにあると言ってもらったのだと、そう感じながら訳した」、そう彼女は話した。
吉増さんに言わせれば「丸投げですよ」と。少年のように笑っていう。
この「丸投げ」という言葉を受けて、丸投げすることの難しさをおもう。
そして私にはまだ、「自分を丸投げする」ことができない、ことに気づく。
たとえばコミュニケーションへの抵抗がそれだ。人と関わり、話し笑い通じ、触れあうことに対してあこがれてきたのに、そのことがこわい。こわい、人との関わりのなかで自分がどうなってしまうのか、誤解されるのか否定されるのか拒絶されるのかわからず、こわい。「自分を丸投げする」ことができない。誤解されるのがイヤで、否定されるのがイヤで、拒絶されるのがイヤ。なんもかもがイヤ、イヤ、イヤ。そんな自分は、「ちいさな自分」にこだわって「ちいさなプライド」を捨てきれない、そんな程度の人間だ、とおもう、そしておもい出す。いつか前に、まったく同じようなことを考えたときのあったことを。
二年前の夏、福島に文学の学校を訪れた時、吉増さんに話しかけた。大学を訊かれたので答えると、彼は遠い大学の先輩なので「頑張れ後輩!」という力強い言葉と共にアドバイスをいただいた。
「触れてみるといい、いろんなものに」。たくさん遊ぶといい、クラブにも行くといい、触れてみるといい。「そうだ吉本隆明さんは何にでも触れる人だったなあ」と。……私はしかし、触れることがこわい、今でもこわい。
触れること、触れにいくこと、の難しさ、抵抗、こわさ
を感じることはつねにある。
自分と他者、自分と世界のあいだに境界をつくり、ちいさな自分を守ろうとする。外の世界と内の世界を隔てさせる。そうして勝手に自分で作りだした境界を自分で越えられなくなる。こわくなって、その境界を踏みだせなくなる。ちいさな自分の世界に閉じこもる。
二年前の吉増さんのアドバイスの後、私には就職活動やら福沢諭吉記念文明塾やら、外に向かって触れること、触れにいくこと、への挑戦の機会が数多くあった。結果改めて「ちいさな自分」を認識した。そしてこのちいさな自分をころしたいとおもった。消え去れと願った。ちいさな自分を消滅させるための手段をずっと考えていた。
そのときに言われた。そのとき近くにいたKに言われた。
「ちいさな自分も、君自身だよ。ころすだなんて言わないで。ちいさな君が泣いている、おまえはいらないなんて言われて、ふるえておびえて泣いている。受けいれて、ちいさな自分を受けいれて」……たしか一年半くらい前だった。
繰り返している。また同じ悩みを悩み、ふたたびの苦しみを苦しみ、考えている。同じことを繰り返している。今でも「ちいさな自分」が自分を主張していて、「自分を丸投げする」ことができない。
そのことに以前から気づけていた、ことに改めて気づいた。もう「ちいさな自分」の責任ではない。私自身の問題だ。
触れること、触れにいくこと、の難しさ、抵抗、こわさ
を感じることは決して悪いことではないと、
逆に考えてみた。そのことそのものが価値かもしれないと。いま書きながら考えた。そしたらこれが「ちいさな自分」に本当にきちんと向きあうということなんだと、判った。ころさず無視せず逃げ出さず、こわさを感じる「ちいさな自分」を受けいれること。その価値に気づくこと。
もうずっと尾崎豊が好きなのだが、ちょうど昨日YouTubeで尾崎の昔の映像を見た。『太陽の破片』をテレビで歌ったときの映像で、この歌が大好きな私は熱心にこの映像を見た。尾崎は何か問題を起こした直後だったらしく、ナレーターが「若気の至りというやつでしょう」とコメントするのに謝ってから、舞台に向った。
尾崎は自分を守るように両腕をぐっと、拘束具でもつけられているような格好で、腕を組むと言うにはあまりに違和感の残る、自分を抱きしめるような姿で、話をしていた。舞台に立ってのちマイクの前でだけ彼は全身から自分を丸投げにして、歌に叫びに音楽に、自分の存在を羽ばたかせていた。
尾崎が自分の両腕を強く抱きしめていたあの姿が目に焼きついて離れない。あの姿は「ちいさな自分」を愛する姿だと、私はいま、勝手におもっている。自他の境界をつくろうが何だというのだ、人とのコミュニケーションがうまくいかないから何だというのだ、「ちいさな自分」が喚くのなら抱きしめてあげるよりほかないじゃないか。
容易にあらゆるものに触れること、触れにいくこと、のできるひとと、そうでないひとがいる。それぞれがそれぞれの生き方で、個性で、私だ。こわさを感じながらも、それでも触れに「いきたい」と思えるものがあれば、触れに「いけば」いい。それだけのことであって、こわさを感じること、をおそれる必要はない。
私 をいだく ということ
私 を投げる ということ
私 を生きる ということ
どこ(どの領域)で自分を丸投げにできるかはひとによって違う。誰しもが違う道を歩んでゆくのだから。どうやって(どんな方法で)自分を丸投げにできるかもひとによって違う。誰しもが違う歩き方で歩んでゆくのだから。いつ(どんな状況で)自分を丸投げにできるようになるかもひとによって違う。誰しもが違うペースで歩んでゆくのだから。
そういうものだとおもって、ここにいま私は文章で自分を丸投げにしてみたつもりだが、これがどの程度他者に向かって開けたものであるか私にはわからない。こうして探るよりほか、私には手段がない。長すぎて読まれないとかは知らない、丸投げだから、退屈でも知らない。それでいいのだとおもう。これが私なりの「自分を丸投げする」唯一の道なのだから。
余話1(
京都に行ったのは舞踏家の笠井叡さんのダンス公演が目当てであった。折角だからついでに四泊滞在することにしたら、偶然、このシンポジウムが行われることを知ったのだった。ここに笠井叡さんと吉増剛造さんが私の中でふたたびつながった。
かつて六年前の春、慶應大学に入学した頃、日吉キャンパス来往舎の十数階の吹き抜けの広い空間で、新入生歓迎を名目に行われた吉増剛造さんと笠井叡さんのセッションを観た。お二人のことはそこで存じあげた。『閃光のスフィア―レクイエム』と題されたその公演が、何に向かう「鎮魂」であるのか当時は考えもしなかった、ただただ衝撃だった、吉増さんの詩の朗読が低く地を震わせ、笠井さんの舞踏が高く空を飛翔していた)
余話2(
冒頭に述べた訳者の一人吉田恭子さんはいまは立命館大学の教授になられたようだが、長く慶應大学で教鞭をとっておられ、大学二年のころ英語の講義で先生だった。五年前の春のこと。
ジョージ・オーウェルの”Why I Write”をテクストとしていた。このタイトルに惹かれて講義を選択したのが落とし穴だった。テクストの中で数ページに満たないこのエッセイ”Why I Write”を読み終えた後は、同テクストに含まれる英国における政治論がひたすら続き、当時の私は早々に興味を失った。”Why I Write”が目的だったのだ。
吉田さんは大らかな人柄だったが、たしか予習を放棄したせいで怒られそれ以降出席を放棄した。当然単位を落とし、必修の講義だったので進級できなかった。反省している。オーウェルといえば、先月『一九八四年』をようやく読んだ。面白かった)