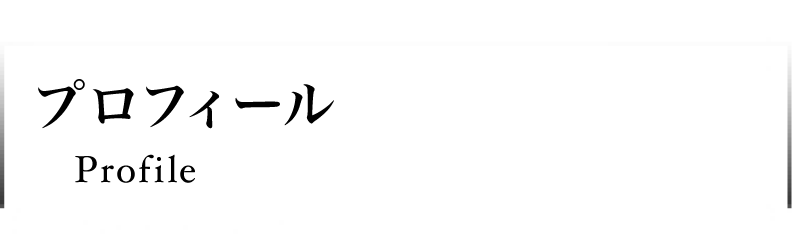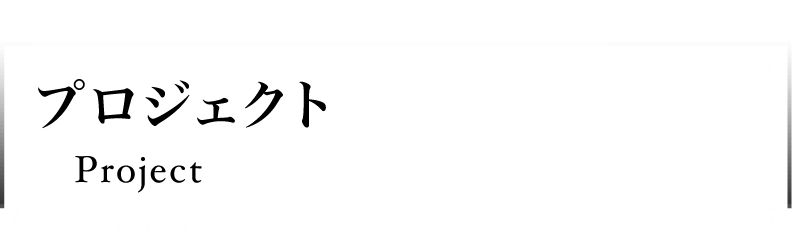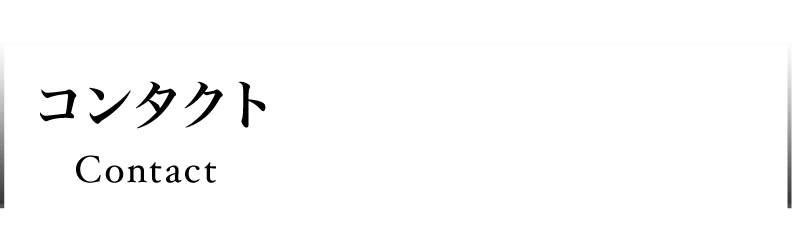「私」は主体ではない ― 古川日出男さんと華雪さんの文学の学校受講録
2015年11月29日
「自分が『開いた』ら、大きな他者が自分の中に入ってくる」
どういうことだろうか?
福島県郡山市にきている。
東京から新幹線で一時間半。ごく近い。
旅の目的は、『ただようまなびや』という文学の学校に参加するためである。
昨年8月に同じく郡山で開かれ、初めて参加した。作家や批評家、また詩人、音楽家、翻訳家などがボランティアで講師として集い、参加者は無料でプログラムに参加することができる。
プログラムの種類も多様で、「短歌から物語を書き起こす」とか、「参加者の過去の記憶から、歴史年表をつくる」とか、「小説家が朗読する声を聴いて、書家が字を書く」とか、日常では触れることのないような経験がここにはある。
小説家の古川日出男さんが始めたこのプロジェクト『ただようまなびや』。今回で3年目、第4回を迎える。
「自分が『開いた』ら、大きな他者が自分の中に入ってくる」という冒頭の言葉は、古川さんによる言葉である。
講師である書家の華雪さんの話で、こんなものがあった。
筆を手に半紙へ向かうと、字に「呼ばれる」のだという。自分が「書きたい字」を書く、のではなく、半紙に「書かれたがっている字」を書く。つまり、主体が「自分」の側にあるのではなく、「創作されるもの」の側にある。
たいていの表現者は、本来そのようにあるものだ。小説を書くにしても、曲を書くにしても、ダンスを踊るにしても、「自分」はどこまでも突き動かされている存在である。インスピレーションは、「自分」で意図するのではなく、「どこかから降って湧いて」くる。
「求められるもの」を見つけ出して、そのものを提供しないといけない。核心はそこにある。
「私」は、主体ではないのである。
では、どうすれば相手の求めているものがわかるか?
どうすれば半紙に「書かれたがっている字」を見つけ出すことができるか?
ここで、冒頭の言葉にあった「自分」を『開く』ということをする。
「自分」を失くしてしまうわけではない。かといって「自分」がすべてでは決していけない。「自分」はありながらも、「自分」にこだわらない状態。「主張する」よりも、圧倒的に「聴く」状態。それもただ聴くのではなくて、相手からインスピレーションを受けるために聴く。
相手に「求められるもの」に、気づける「自分」でいること。心を閉ざさず、オープンに相手に関わっていける「自分」でいること。
それが理想的な、 「自分」を『開いた』姿である。
自分を開いたら、あとは、開いた自分に、相手が入ってくる。大きな他者が、自分の中に入ってくる。
「大きな他者」というのは、特にものを作る過程での感覚だ。自分ではないなにかが、自分を乗っ取り、自分を演じさせ、自分を通過していく感覚。華雪さんが半紙の上に字を見出すことも「大きな他者」とのふれあいであり、古川日出男さんが物語を書く、あるいは朗読することも「大きな他者」とのふれあいである。
「大きな他者」が作り手を突き動かす。それはインスピレーションの源泉となる、目には見えない存在なのだ。
ものを作ることは、「自分」と「大きな他者」との触れあいであり、未知とのコミュニケーションである。そして、ものを作る行為からは遠い人にも、その触れあい自体は遠くない。日常生活の中における何でもないようなコミュニケーションの中で、同じことがいえる。
私たちは、自分を開いて、「求められるもの」に気づこうとすれば、日々大いなる未知と触れあって生きていける。そうすることで、より豊かな、出会いに満ちた日常を送っていくことができる。