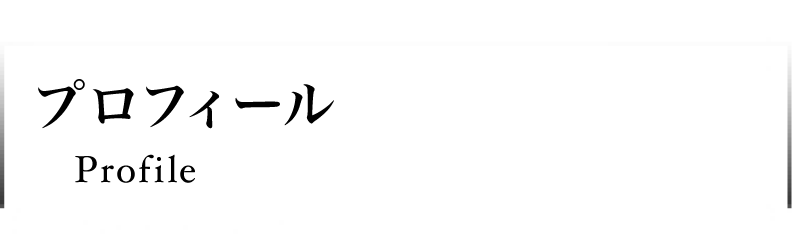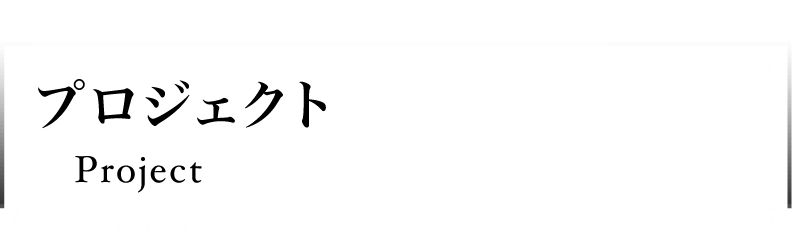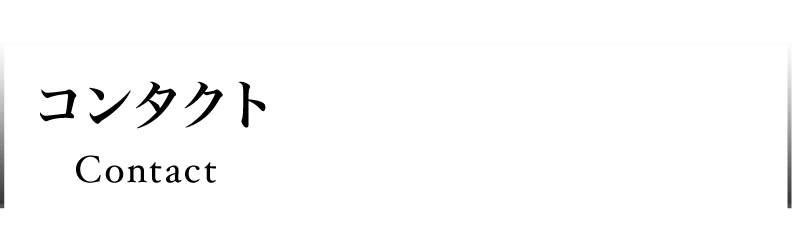生活は詩に優先する ― 谷川俊太郎さんのインタビューを聴く
2015年11月17日
「詩よりも生活が大事だったんですよね、一貫して」
意外に思われるだろうか。谷川さんがこう言っていることに。
「どうやって食っていくかが最大のテーマで、いい詩を書くことよりもどうやって金を稼ぐかということが、十八歳から二十歳くらいにかけての、自分の最大の課題だったわけ。だから生活が詩よりも優先してるということが、一貫してぼくにはあるんじゃないかと思うんですよ。詩を楽しんで書いているときにも、どこか生活の方が大事だ、生活の方が問題だ、という意識が自分にあるのは確かなのね」
彼の詩は、小中学校の教科書にも引かれ、また合唱コンクールの課題曲にもなっており、どこかしらで一度は目にしたことがあるだろう。
「万有引力とは/ひき合う孤独の力である
二十億光年の孤独に/僕は思わずくしゃみをした」
(谷川俊太郎「二十億光年の孤独」)
こんな一節は、記憶を手繰ればきっと思い出せるはずだ。
(谷川さんが、二十一歳の時に出版した処女詩集の一篇)
「詩」という言葉に関心のない人は、あまり興味がないかもしれない。
でも詩とは、実は誰しもに身近なものであるはずなのだ。
たとえばInstagramをやっているだろうか。日常のひとコマを写真に収める行為。風に揺れる一輪の花、光さす石畳の道、微笑みに満ちた女友達の顔、オシャレなレストランのデザートとラテアート。タイムラインにあがってくる写真は、数多のひとの、眼に映った景色。
たとえばTwitterをやっているだろうか。瞬間の思いを言葉にして紡ぐ行為。道ゆく途中で会った猫のこと、冬の透きとおった空気にひろがる空、職場での笑える話、恋人とのささやかな惚気。タイムラインにあがってくる言葉は、数多のひとの、心に映った景色。
そのどれも、詩になりえる、この世界の美しい欠片である。
「街には詩があふれている」と谷川さんはいう。
そして、「どんな人間も詩(ポエジー)を感じている」と。
誰もが言葉を、そして写真を発信できる時代。発信された言葉や写真は共感され、シェアされていく。今の世はそういう時代。「詩」そのものに関心がなくとも構わない。誰しも「詩」が世の中にあふれていることを知らずして、実は「詩」を感じながら生きてる。
「詩は常に無言で存在している
それに言葉を与えるのが人間」
(谷川俊太郎「朝陽」)
もちろん普遍的な、言葉が個人に結びつくような詩作品を書くには、それなりの鍛錬と洗練とが必要となる。しかし詩とはなんの関わりもなく生きているつもりでいるひとの書いた言葉、撮った写真が、ハッとさせられるような美しさを宿すこともある。
生活をしていない人間など、いないのだから。そして生活が詩に優先されるとはつまり、詩が生活に内包されているものなのだろうから。
まず詩というものの身近さを、僕らはもっと感じていいんじゃないか。
「生活が詩よりも優先する」
六十年以上の時をかけて、詩作に励んできた谷川さんがそのようにいう。
詩人の生活とは? 想像つかない。でも人間として、やっていることはたいして変わるはずもない。朝起きて、ご飯を食べて、外を出歩いて、仕事に打ちこみ、あるいは家の中にいて本でも読み、テレビを見、排泄をし、風呂に入り、またご飯を食べ、睡眠をとる。
そんな程度のことしか、人間してない。
何が違うのかというと、何を見ているか、何を聴いているか、何を感じているか。きっとそれがすべてで、逆にいえば、それくらいの違いしかない。
それくらいの違いしかない。
「ぼくはいつ詩に捨てられるのだろう。捨てられたら松の木の見え方が変わるだろうか。女のひとの見え方が変わるだろうか、もしかすると海の見え方も、星の見え方も」
(谷川俊太郎「十七歳某君の日記」)
谷川さんがもし詩に捨てられることで、世界の見え方が変わるというのならば。
きっと僕たちは、日常の中に詩をもつことで、世界の見え方を変えられる。
より注意深く、街にあるちいさな美しいもの(=詩)を見逃さないように生きていくことで、僕たちは、もっと豊潤な世界に生きられる。彩りあざやかな世界がみえてくる。
世界を変えるのは、僕らの視点なのだ。
11月3日、文化の日。
御歳八十三、谷川俊太郎さんのインタビューが行われるというので、声を聴きに、存在を感じに、新宿朝日カルチャーセンターに足を運んだ。
これはその簡潔な記録である。