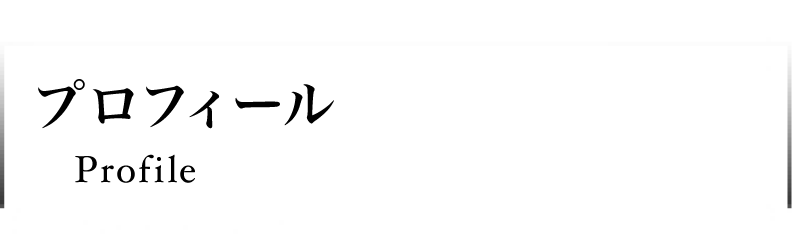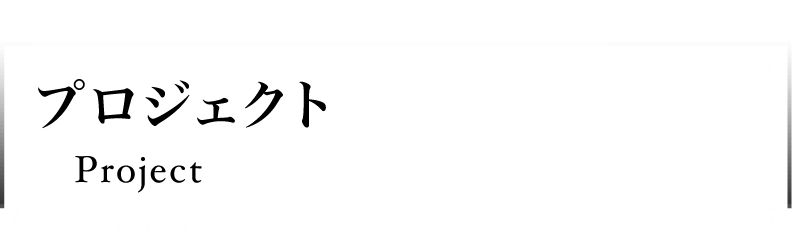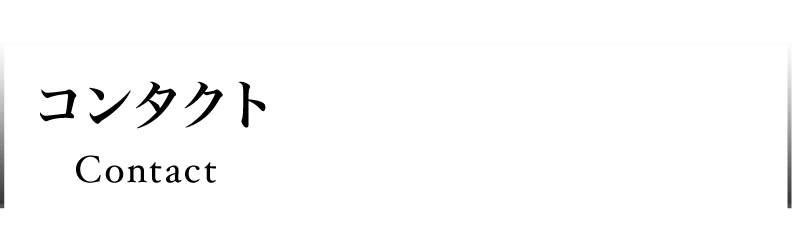人類愛と厭人家の密接な関係 ― 中島京子作『宇宙エンジン』を読んで
2014年10月3日
中島京子『宇宙エンジン』(角川文庫、2012年8月)
下記には、物語の結末に関わる内容が記されています。
ついには小説内に登場することのない、ひとりの人物をめぐる物語である。その人物はエンジンカと呼ばれていた。人嫌いの厭人家。世を厭い山に籠もり、消息不明となっていた。
彼には、彼が存在を認知していない娘がいる。わが子の宿ったことを知る前に、彼は行方をくらませてしまった。彼の娘、蔵橋ミライは奇妙な縁で知り合った青年葛見隆一と共に、わずかな情報を手がかりとして、父親を捜しはじめる。
自分の過去が、なんていうんだろ、空白なのがちょっと怖いような気がしたの。誰にも聞けないってことがね。誰かの記憶には残っているというのと、誰の中にもないってのは、同じ知らない状態でも、なにかが大きく違うのよ。(p.24-25)
これがミライの行動の端緒となる。ミライと隆一は、父親と関わりのあった人々に会い、奥底に埋もれていた記憶を掘り返し、忘れ去られた過去を呼び戻す。ゆえに父親の姿は、様々な人から伝え聞いた話として語られることになる。
「『私は人類を愛しているのだが、人類一般を愛すれば愛するほど、ひとりひとりの人間に対する憎しみが深くなる』ってやつだ」
と、S教授は言った。
「なにそれ」
「ロシアの文豪の小説に、そんな話が出てくる。人は理想を追い求めると、実際の人間の愚かしさに耐えられなくなってくるんだろう」(p.158)
伝え聞いた話が語られるのは、この小説の特徴と言える。語り手が次々現れては、物語が勝手に進行していくのだ。そもそも作品自体、小説内作家が後に隆一から伝え聞いた話として書いた小説という構造を取って書かれている。
記憶は曖昧である。いつしか自分に都合のいいように書き換えられてしまう。そして誰も気付かぬまま、真実は失われゆく。作者はここに記憶と真実の記述を試みた。幾人もの語り手が登場する複雑な構造を取ったことで、ミライの父親当人をヴェールに包み、語り手の主観によって語られる話でしか彼の存在を浮き上がらせない。
「大げさですけど、真実ってものを捕まえるのは、ほんとに難しいやって、思ったんですよ」(p.242)という隆一の言葉通り、捕まえづらい真実をより曖昧に、曖昧だからこそ読者の想像が働くように仕向けている。誰もが口を揃えて言うのは、彼が〈宇宙的規模の厭人家〉だということだけだ。
先の引用で言われていたロシアの文豪とは、ドストエフスキーを指す。該当する部分は『カラマーゾフの兄弟』に見受けられる。これも、修道院のゾシマ長老によって「ある医者」が話したものして語られる伝え聞いた話としての言葉である。
わたしは人類愛に燃えているが、自分で自分に呆れることがある。というのも人類一般を好きになればなるほど、個々の人間を、ということはつまり一人一人を個々の人間として愛せなくなるからだ、と。
(ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟1』亀山郁夫訳、光文社古典新訳文庫、2006年9月、p.149)
ミライの父親が何を目指していたのかは語られない。当人が出てこない以上、推測するしかない。しかし愛したはずの女を捨てて、つまりは隣人愛を放棄して、活動家として政治運動に加担しながら人類愛へと向かった彼は、何を為しえることもなかった事実だけは明らかだ。
行き過ぎた人類愛については、ニーチェが以下のように言っている。
人間をもはやそれ以上消化できないのに、胃の腑は人間で一杯という状態――これを称して、人間に倦み飽きたという。人間嫌いとは、あまりに貪欲な人間愛の結果であり、「人間食らい」の結果である。
(フリードリヒ・ニーチェ『喜ばしき知恵』村井則夫訳、河出文庫、2012年10月、p.244-245)
ひとり山に籠もったミライの父親は、映画を録画したビデオテープを友人に送ってもらいながら、始終それらを観て過ごしていたという。「受け入れ、許し、愛せ」というシーンを何度も、何度も巻き戻しながら毎日泣いていたという。彼は「あまりに貪欲な人間愛」の末路を辿った人間なのだ。
ただ後に残されたのは、新たに生まれてきたミライの存在。彼がその生命の宿りも知らない、いつまでも繋がってゆく人間の営みの証。その真実は、「憎しみと報復、暴力と殺戮の、永遠に終わることのない連鎖が、人間の本質だと思ってしま」(p.344)うような厭人家にも対抗しうる。娘にミライと名付けた母親が、「アカルイミライを信じて生きていくこと」をミライの父親に向かって語ったように。
捜していた父親は、最後まで小説内に登場しない。しかし隆一がミライの言葉を小説家に語ることによって、小説としては終幕を迎える。「もともと、自分の目的は、父親を捜すことじゃなかった、自分の誕生に関わる記憶を持つことだったって言うんです」(p.357)。さらには彼女が求めていたのは、「自分がこの世に生を享けた、ポジティブな理由みたいなことだと思います」(p.335)
ミライは父親捜しの一件を通して、隆一と恋仲になっており、やがて小説家に子供の生誕を報告する。また時代を超えて、新しい生命が生まれる。