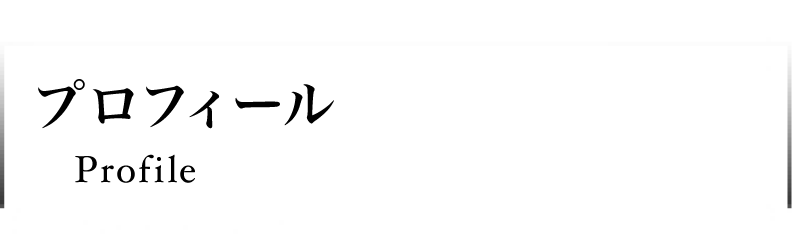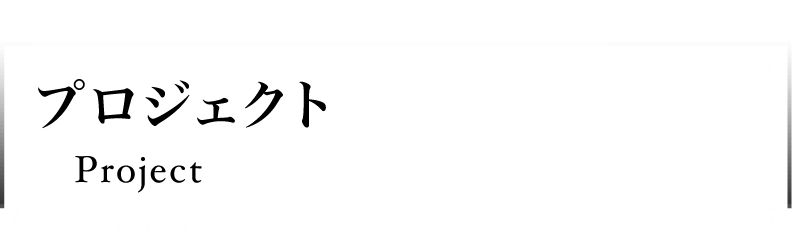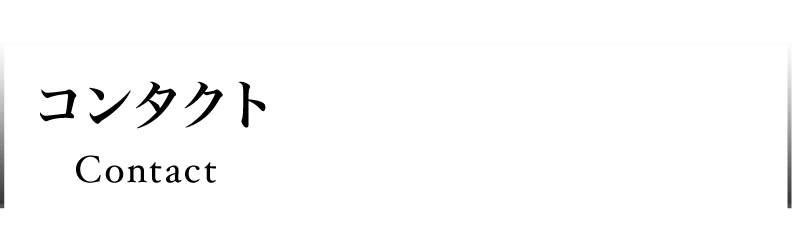生を舞う女性たち ― 中川龍太郎監督『Plastic Love Story』を観て
2014年1月26日
男性性への罪の意識が、これほど丹念に描き込まれている作品は珍しい。中川監督は自身の性を強烈なまでに批判する。その批判的な映像は時に滑稽だ。逃れようとしても逃れられないのが性である。
私たちは、私たちの性を表象するこの身体に閉じこめられ、生きている限りは抜け出ることができない。化粧したり女装してみたところで気を紛らす行為に過ぎない。性の中で足掻き、苦しむ。そしてついには自分を殺す。死に至るより他に、自身の性を放棄する手段はないからだ。その意味で作中の男性人物はみな破滅的である。
中川監督は男性に徹底して冷徹な眼差しを向ける。しかしその眼差しは自身をも突き放した客観的視点で描かれるため、観客が作中の人物に嫌悪感を抱くことはあまりない。むしろどちらかといえば、滑稽なものとして笑うのだ。
たとえば清掃員の男が女子学生に恋をして、数々の無理難題に応えようとする姿。見すぼらしい格好で要求されたバラを百本抱え、大胆にも学生たちが大勢いる教室の中へ入り、女子学生に愛を告白しに向かう。そこにロマンティックさは欠片もなく、ひたすら不器用な男性の、伝えがたい思いが表出されるだけだ。端的に滑稽なのである。女子学生はバラの花束を突き返し、清掃員の男は取り残される。これ以上なく惨めな男性の姿がそこにある。
その姿を見て、観客は何を思うか。その滑稽さを心の奥底で笑い、自分ならもっと上手く思いを伝えられるとでも感じて優越感を抱くだろうか。いやそうではない。本心では誰もがわかっている。人間と人間の関係は、総じてこの清掃員の男の滑稽さに通じるものがあるのだということを。自分の純粋な思いが思うように伝えられず、一方通行の感情ばかりが膨れあがるものが人間の本質であるということを。
つまり中川監督は男性の惨めで滑稽な姿を作中に描くことで、人間に普遍としてあるコミュニケーションの齟齬を映し出しているのである。交わりえない人間と人間の関係性の哀しさを、性の差異によって浮き彫りにしようというのである。
今挙げた一つの例は見すぼらしくも無垢な男の純愛だ。対置されるものとして作中には、自制しない男性の肉欲が渦巻く様子があり、罪の意識を増幅させる要素として働いている。これもまた一方的な感情として描かれることになるが、そこに人間と人間の関係性はない。男性の飽くことない性欲と、その性の捌け口となる女性とがいるだけだ。それはもはや人間同士の関係ではない。
そうした描写を観て思うのは、男性は明確に自身を罪なる存在であると認識すべきだということである。悲観的な考えかも知れない。罪の意識を抱え込み逃げられない身体に閉じこめられたまま、絶望するしかないのだという現実は。それでも男性は自身の性にもっと意識的にならなければいけないし、中川監督の冷徹な眼差しが映画を通して現実に結びつく地点は、そういうところにあると感じる。
一方で、男性性の罪なる意識などとはまるで関わりがないかのように、高らかに女性の姿が描かれるのも中川監督の作品ならではだろう。これまで作中に描かれる男性性を論じてきたが、この作品では実のところ、男性は女性を引き立てる役割を第一に担っていると言って過言ではない。この映画はなによりも、エゴイスティックな男性によって尊厳を傷付けられつつ、したたかに世界を生き延びようとする女性への讃歌なのだ。
なぜこうまで遠回りしてきたかと言うと、すべては男性の滑稽さを表したいがためである。こうして映画の批評を書いている私自身男であるから、この作品による男性性への批判的視点からは免れえない。しかしながら男性がそうして煩悶することを尻目に、女性はさっぱりとカタルシスを得てこの映画を賞賛することになるだろう。男性性への罪の意識がどうとか言うことは女性にとってはまったくどうでもいいことであって、そんなことを長々と語ってきた私こそ滑稽であるのだ。
さて、そうはいっても女性には女性の苦悩がついて回るのは当然のことである。主演の女性たちは三者三様、環境も境遇も違う。共通する点はといえば、どこか空虚な、人間の生への感動を失っていることであり、それぞれがそれぞれの苦しみの中にあることが見てとれる。
中川監督による文章から引用しよう。
例えば、夕日眩む東京の片隅に、恵理という名の女性がいた。腹部に宿る確かな命の感覚に微笑む恵理。その瞳には、自殺した中学の同級生・康臣の影が揺らめく。そんな彼の姉から手渡されるビデオテープ。そこには、彼女の知らない康臣がいた。見えている景色。聞こえている音。そのすれ違い。他人。すでに廃校となった母校を訪れた彼女は、彼が残したもう一つのテープを目にする。そして、彼女は、茜色に染まる静かな図書室で一人、そっと手を振り上げていた。
例えば、都会のある寒空の下、理奈という名の女性がいた。円満な家族関係、気心の知れた友人との学生生活、容姿端麗な彼氏、そして足の怪我とともに失くしたかつてのバレエへの夢。思い描いていたものとは異なる日常の中に理奈は埋没していた。そんなある日、彼女は、祖母の介護をする傍ら、清掃員として生計を立てている透に言い寄られる。今とは違う現実を生き直すように詰め寄る透の決死の想いを背に、彼女は、立ち並ぶビルの屋上で一人、軽やかに両腕を広げていた。
例えば、海に臨む小さな田舎町に、奏恵という名の女性がいた。幼い頃に弟を亡くした奏恵は、高校をサボっては、かつて弟と遊んでいた海辺の廃小屋に一人足繁く通っていた。医院を構える父のもとで療養中の心を病んだ美しい青年・潔が、自分と似た孤独感をもつ奏恵に対して、不気味な笑みを差し向ける。若くして彼との子を身籠ってしまうが、その命は日を見ることはなかった。疎通し合わない言葉。自傷する自己愛。それでも、彼女は、小波揺らめく波打ち際で一人、祈るように両手を掬い上げていた。
この作品ではそんな女性たち三人の生き様が描かれるのだが、物語は最後になるまでまったく交差することのない人生である。ばらばらの断片となって組み合わされ、どこまでも独立した物語として進んでいく。ただひとつ彼女たちが選ぶ道だけが通じている。生きることへの決意の道だ。
生きようとすること、それは場合によってはとてつもなく重い選択である。時に死ぬことの方がたやすいのかもしれない。現に、作中で自身の罪を意識する男たちはみな死にゆく存在として破滅していく。
にも関わらず、彼女たちは軽やかに生を舞う。滑稽な男たちを置いて鮮やかに前を向く。どこまでもしたたかで、悪びれない。まるで「私は生きる」と言い放つかのように。颯爽と過去に訣別を告げ、自信に満ちあふれた表情でこれからの道を歩みゆく。
そんな女性たちの姿が観客に勇気を与える。生きることを選択する勇気を。この映画はあまりにも重い題材を取り扱っていながらにして、あまりにも軽やかに生きることを選択する女性たちが登場する。断片的な個々のエピソードに捉われることなく、映画全体を俯瞰して観たとき、彼女たちがどんなにか生き生きと変化を遂げ、最後のシーンでの表情を生み出したかがわかるだろう。
そう。波乱の過程を経た終幕で彼女たちのその表情を見たとき私は、思わず涙せずにはいられなかったのである。