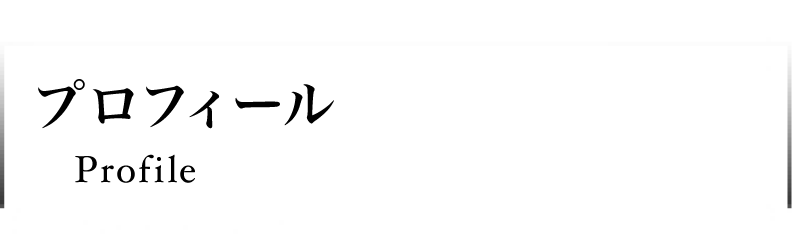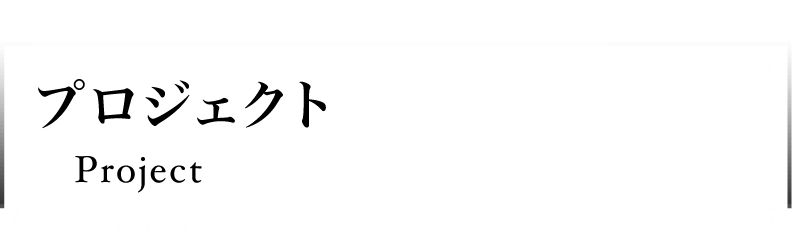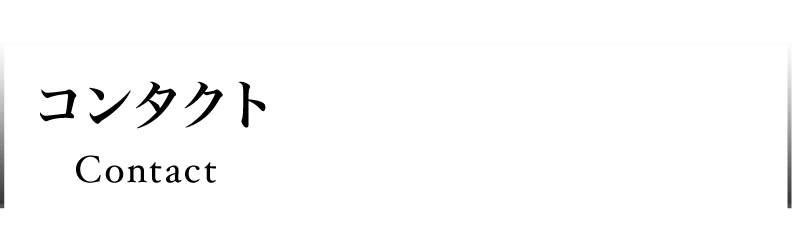『ここと今』のアートのために


2019年2月、山梨県北杜市清春芸術村での滞在制作により始動したパフォーマンス・アート・プロジェクト。
作家・詩人のテクストを用い、原文の構成を解体しながら、その場でシーンを生成する演劇作品を上演する。俳優の身体と感覚器官を通して、再構築されたイメージと言葉の連なりを、『ここと今』の空間に立ち現わす。 それによって、テクストの彼方へと向かい、「ここと今とが問題でなくなるとき 愛はいちばん愛そのものに近づく」(T・S・エリオット)ことを、『ここと今』のアートである演劇であらわしたい。これまで扱ってきたテクストは、アーノルド・ウェスカー、アントン・チェーホフの戯曲、宮沢賢治、原民喜、パウル・ツェランの詩など多岐にわたる。
また、分断されていない空間に共にあることが必要だと考え、舞台面と客席を分けることはせず、観客と俳優はひとつ同じ空間の、すきな場所にすきなようにいてもらう、という共存のありかたを模索している。
ことばが立ち現れる瞬間 〜ワーク・イン・プログレス上演〜
創作の「場」に居合わせる。ということは、俳優や作品が変化し、今まさに変容していく生々しい瞬間に立ち合うことを意味しています。そこは、人と人とが真正面から関わりあうクリエイティブな「場」です。 やがて、見ている者の心が感化されはじめます。人間の脳には、ミラー・ニューロンという、変化を敏感に受け取り反応する機能がついています。目の前で起こる変化がまるで自分のことのように感じられるとき、変化はまぎれもなく「見ている者の心」のうちに起こるのです。
では、その「変化」は何に対して起こるのか。ざっくり言えば、普段は意識していない「からだ」や「ことば」の認識が変わっていきます。つまり新しい「ものの見方」が生まれる瞬間に立ち合い、その変化を自分のものとすることができます。今までにない発想や認知が生じることは、ルーティンの日常を打ち壊します。アートとは、従来のみずからの価値基準を揺るがし、未知の世界へと引きずりこんでくれるものです。そして演劇とは、「今ここ」で「人間」が変化する瞬間を目撃できるアートです。
ワーク・イン・プログレス写真
指針としてのキーフレーズ
1.
魂の対話をする。
*
人間的である、とはいかなることか?
目の前の人間を非人間的に扱わないこと。一個の人間としてみること。
*
「わたし」の構成要素やラベリング、カテゴライズを外した一個の人間として、一対一の関係性を見つめ直すことで、目の前の相手をわかろうとする態度を示すこと。わかりあおうとする努力。
そのために自意識を手放して、「わたし」という幻想から解き放たれること。
そのために「他者」の言葉=テクストを発するプロセスを経ること。
*
「わたし」を媒介として役の魂を解放する、昇華する。媒介になった「わたし」もまた。そして、観客もまた。
「ここと今」における変容が生じ、観客がその変容に同調する。ミラー・ニューロンを発火させる。
*
芸術家、としての役者の生を試みる。
*
「悪いのは、僕らが身近な者を十分に愛さないことじゃありませんか」(チェーホフ「書簡」スヴォーリン宛、1888年10月18日)
「芸術家は、創作にさいして作品の発現のために自己自身を根絶する通路のようなものとほとんど同じである」(ハイデガー『芸術作品の根源』)
2.
ストーリーテリングのための劇ではなく、言葉と沈黙の断片の重なりから浮き彫りになってくるものを捉える。
*
精神科医のフリッツ・パールズはゲシュタルト心理学に関して、創造的な誤読をした。「物の構成を変えることによって、世界に何かを加えることができる」と。現代物理学において、これは真実だ。質量は保存されない。
*
断片同士から、イメージを結びあわせるパターンを現出させることによって、美を知覚できる場をつくる。そのために「ここと今」で起こることに、観客も役者も繊細に気づいて反応すること。
*
「全体は部分の総和より豊かである」(ゲシュタルト心理学)
「寄せ集めた全体が部分の和より大きくなるのは、部分の組み合わせが単なる加法ではなく、乗除法あるいは論理積の形成といった性格をもつからである。合体の瞬間に閃きが走る、とも言えようか」(ベイトソン『精神と自然』)
3.
「愛は愛の対象の弱点を見えなくする、と人は言うかも知れない。しかしこの命題は逆転させることもできる。すなわち愛は愛の対象の長所に対して目を開かせる、と。無数の人たちが何も感じることなく、そのような長所の傍を素通りしていく。その中のひとりがその長所に眼をとめる。そしてまさにそれ故にこそ、愛が魂の中で目覚める。一体そのような場合、その人は何を行ったのだろうか。多くの人たちが持たなかった表象を、その人だけが持ったのである」(シュタイナー『自由の哲学』)