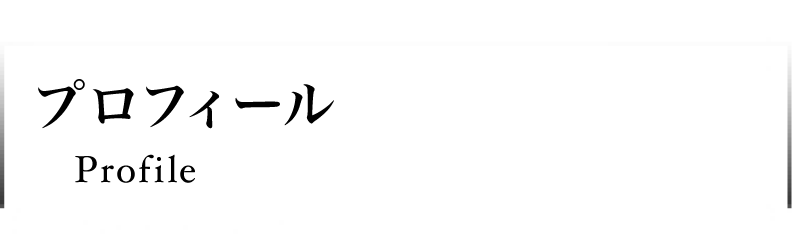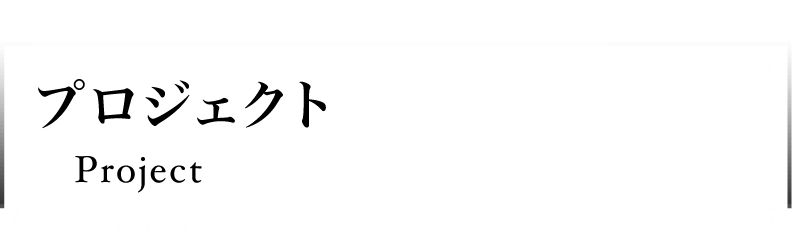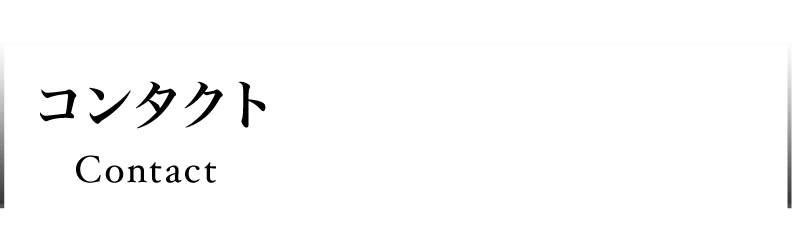劇作家・演出家 坂手洋二氏へのインタビュー
話し手:坂手洋二(劇作家/演出家/劇団燐光群主宰/日本劇作家協会会長/岸田國士戯曲賞選考委員)
聞き手:酒井一途(ミームの心臓主宰)、岩渕幸弘(思出横丁主宰)
演劇公演企画『学生版日本の問題』(2011年12月上演)に寄せてのインタビュー記事の採録。各肩書は2011年当時のものです。
■俳優の身体の違い
酒井 坂手さんは大学の演劇の教育に関してどう思われますか?
坂手 レギュラーで入るのはずっと断ってきた。単発なら集中講義やワークショップしたりはしているんだけど。海外でもオーストラリアの国立演劇大学で卒業公演の演出をしたりとか、アメリカなんかでも。
酒井 アメリカでやってみてどうでしたか?
坂手 面白いよ。若い人たちでも身体が違うじゃない、西洋人と東洋人って。
酒井 インドネシアの俳優の体つきが全然違うと以前仰っていましたね。
坂手 そう、西洋人とアジア人の違いもすごくある。
酒井 演劇においてはどういう違いが出るんですかね?
坂手 それは意識と無意識の両方の部分だからね。演劇の場合はそれを使っていくということもあるし、表面的な違いを使いすぎて安直になってしまう場合もある。さっきのアメリカの若い人なんかは身体に力があり余っている面白さがあったりする場合もある、勘違いも含めて。日本の人は力入れないのが流行りすぎているから。例えば、力を入れようとしてみた身体と、入れようとしなかった身体の違いってのは、歴然と出てくる。
酒井 逆に日本人俳優の良さみたいなものはありますか?
坂手 資質としての特徴はまとめきれない。「日本人」と表象されることはあるけど、それって性質じゃなくてたんに習慣じゃないかな。僕ら演劇を作る人は「この人はこういう人だから、こういう行動をする」という判断をやっちゃいけない。
酒井 ステレオタイプの人間を書いてはいけない……?
坂手 そう、でも「よくある」という意味でのステレオタイプ批判ではなく、「人間ってこういうもの」というのに発展してゆくのが良くない。枕としてはこんな感じでいいかな。
酒井 はい。ありがとうございます。
■演劇という表現活動の魅力
坂手 演劇って表現を選んでる理由は、一種の多相性を表現しやすいからなんですね。同じ問題も見る角度で全部違うわけだから。小説家なんかの場合は、小説家自身の人生と登場人物の人生とのポジショニングの擦れからわかる世界観を読者に委ねながら、多相性を持っていることを保証しようとすることもあるわけですよね。だから逆に芝居がかってしまう作家もいるわけです。
演劇の場合は、僕の日本語で言うと「創作主体の所有格がない」。「表現の所有格がない」と言い換えてもいいんだけど。演劇では「これは僕の表現です」っていうのが成り立たないんですよね。集団創作だからということだけじゃない。僕と同じような育ち方をして、同じような環境で育って、誰かが同じように思ったことがあったとしたら、それはつまり「僕」じゃなくていいじゃない。表現ってのは実は疎外で、「私です」って言えば言うほど、疎外される。そういう方向のリアリティに見合った表現が演劇です。
「自己表現」って言葉が80年代にすごく流行ったわけ。僕は当時からそれを批判してたんだけど。「自己表現」や「自分はなんか分かってるんだぜ」みたいなね、たとえば「来年流行るアイテムはこれだぜ」って発言するアーティストが時代の先端にいるのだと錯覚して、表現をすること自体が時代のお先棒を担ぐお仕事であるっていう誤解をしてる人が多かった。
酒井 演劇を表現するにおいて、主格が存在しない方が良いという……?
坂手 しない方が良いとかじゃなくて、そういうものなんだと知ってるかどうかってこと。「表現の所有格」はないんじゃないかっていう仮説ね。稽古場では、誰かのアイデアで物事が進んでいくこともある。演劇ほど「あれは俺がやったんだ」っていう言葉が似合わない表現はないね。たとえば「この下手な役者どうすんだ」って時に、彼をまともに見えるように色んな算段をしたとしても、それはじつは「処理」として進行するんだが、舞台に出せば「創作」という扱われ方になる。演劇の良さは、そういうふうに主体性や所有格がある意味、溶解してるところにある。
酒井 そこに演劇の魅力を感じる、と……?
坂手 魅力と言うか、その仕組みを基にしないとできない取り組みや問題があるんじゃないかということ。
酒井 その多相性が存在するからこそ、初めて向き合える見方というか、より多様性のある視点が持てるんじゃないかっていう。
坂手 その多相性が目指されてはいない。
酒井 それは自覚されてないからですか?
坂手 違う違う。もちろん自覚してるわけだけど、多相性を目指すんじゃなくて、元々多相性はあるべき。
酒井 手段であって目的ではない?
坂手 そうですね。
■80年代の表現活動
坂手 良かった面は、まだ大学が解放されていた状況が少しあって。サークルでも24時間泊まりこめたりしたり。僕は大学の演劇部に一年くらいいたけど、僕らがアルバイトして50万貯めて照明機材買ったり。長く残っていた慶應の劇研の照明の大半は僕らの年代が買ったやつ。
酒井 そうなんですか(笑)
坂手 学生なのに自分でバイトして買って大学に寄付してたの。そういうことをなぜやるかというと、やっぱりそれは大学を一種の解放区、「僕たちの場所」だと思ってたわけで。80年代には表現する人たちの解放された場という意味でも、文学や、踊りや、音楽、演劇含めていろんな人が集まって、何かのイベントをやることが非常に自然だったの。「大学の自治」が認められていた時代だからね。
大学以外でも、日韓の問題の為にとか、集会やイベントをやったり、山谷の労働者の為に労働者会館を作る寄付のためにイベントをしたり。89年に昭和天皇が死んだわけだが、そのずっと以前から、社会全体が喪に服すということで「自粛」をするだろうと言われて、色んな報道とかメディアでも歌舞音曲が禁止されるだろうという予測がされ始めていた。僕らアーティストたちとしては、天皇が死んでも自粛しないというその一点のために超党派が集まる組織を作ろう、となったわけ。その中心が京都大学西部講堂なんだけど、学生も含めて学生じゃない僕らもそこの「連絡協議会」に入会してた。現在までも大学の講堂を完全に乗っ取っているわけで、年齢も何処に住んでるかも無視して有志の皆が集まって、天皇が死んだら四日三晩ぶっ通しの反「自粛」イベントを96時間やり続けると決めて、実際にやったの。
酒井 すごいですね(笑)
坂手 「CRY DAY(クライ・デイ)」という組織なんだけど。寒かったよ、あの時は。1月の京都だから。意地になって96時間やった。夜中はね、映画やるわけ。映画を上映して、一人でも客入れなきゃイベントとして成立していないということで意地になって、誰か酒飲ましてでも客席に座らせて無理やりイベント空間を継続させていくという。表は焚き火をやって、焼酎売ったりニンニク焼いたり。右も左も殴り込みに来るって言うんでかなり強固なバリケード作った中でイベントをやってたのね。
あと東京でも大喪の礼っていうのがあって、天皇の葬式が新宿御苑で行われた。その日に、同じ新宿の中で意地でもイベントやるって決めて、僕と音楽評論家の平井玄って二人が中心的になって、テレビのモニターに大喪の礼の光景を流しながら、一日中イベントをやった。同時多発で「秋の嵐」という団体もあれこれやっていた。いっぱい逮捕された。不当な別件逮捕。その時も色んなジャンルの音楽も踊りも集まって来るし、その頃は東大の寮の前の広場とか他にも色んなところでイベントやってきていた仲間がいて、アカデミズムの人たちや在日の「指紋押捺拒否」関係の団体だとか沖縄研究会の人たちね、あとは特攻隊の生き残りの「わだつみ会」とか、そういう人たちも一緒に。キリスト者の会もあった。みんな集まってくれて、テレビなんかの取材も来る。もう錯綜してるわけ。そういう意味では非常にアジア的な混沌の状況があってね。当時の僕はまだ二十代なんだけど、同世代の多数派からは完全に浮いてはいたかもしれない。
酒井 二十数年前ですか。
坂手 うん。だから僕が岸田戯曲賞をもらった時に、西堂行人さんなんかがびっくりするわけ。「完全にアウトサイダーなのに」って、そういうことを言われた。僕の80年代はそんな感じ。
■岸田戯曲賞に選考される現代演劇
酒井 その頃はそういう熱気があった時代だと思うんですけど、現代では岸田戯曲賞の選評とか批評を見ていても、家庭の事しか書いていないとか言われていて。表現の手段としても随分内向きになってきてると言うか、すごく小さなところに行ってると思うんです。
坂手 それはね、ものすごく難しいんですよ。例えば僕があまりぴんと来ない受賞作が、「それでも何かの現実を反映していますよ」と言われると、そうですね、そうですか、と言うしかない。演劇という手段を選択して「とりあえずこういう作品を作ることでいきますよ」ってやってみた、そのことはマルなんですよ。ただ。中途半端に認められちゃうと、そこの段階で自作を模倣して再生産することになっちゃう。彼らがそのままで行ってしまうのかこれから変容していくのかは、僕にもわからない。
■演劇の収入源として
坂手 劇作家協会の戯曲セミナーを十年以上やってるわけだけど、僕が始めたときに「申し訳ないけど、セミナーを劇作家協会の収入源にする」と。シナリオ作家協会がやっているシナリオ研究所(現・シナリオ講座)みたいに。一般科はもうカルチャーセンターでいいと。本当に書きたい人はその中で人脈を作るだろうし、講師とのコネクションとかね。そして一般科の先に、将来は研修科をやると。それは何年後かに実現した。
ただ三年後、一般科の段階で、斎藤憐さんがもっと専門的にやりたいと言い出して。「俺はなんか良い作品が生まれてこない気がする」って、憐さん流にゼミナールや添削指導を始めて。「インターネット講座」まで始めちゃったわけ。するとインターネット上でもう戦争が起きるわけよ。講師と受講生が喧嘩になったりして。「だから言ったでしょ」っていうのもあるんだけれど、紛糾して、元に戻した。そういうセミナーに集まる人達って、一般的な技量の問題として色んなことを知ることができたり、加えて、人脈を作れたりとか、質問をしたりという相互性の中での会話が欲しいから、来ているわけで、いきなり高レベルの個別指導というのはリスクが高いわけです。だから、戻した形は、カルチャーセンターに近い部分もあるんだけれど、「劇作家協会は収入源としてこれやります」ってしゃあしゃあとニコニコと言ってもいいのだと思う。「それでもちゃんとしますよ」ということです。だからそれは一種の「現実」を伝えてもいるわけね。それも一種の「批評」なんだ。問題はその在り方。一方通行も困るけど、相互性をあまりにも予定調和することもまた気持ちが悪いわけで。
俺は、初心者体験型ワークショップというのが苦手でね。「演劇ってこんなに楽しいんですね」って、「やってみたらこんな風でしたね」って、そういうのがなんかもう、大嫌いで。そんなことでお金貰って全国行ってる奴ら、皆やめろよって思うよ。そういうものがどうして仕事になるかっていうと、参加した何十人かをみんな喜ばせてまた呼んでもらうしかないわけ。そのことが正しい生き方なんですか、っていうことなんだよ。
■改めて『日本の問題』について
坂手 お客さん呼ぶために何やってもいいのかという問題に矮小化しないで、それは、演劇がいま「どのように存在させられているのか」というふうに見れば、深い問題になるかもしれない。
人によって違うでいいんじゃないかと思うけど、僕はどちらかというと、自分自身が何をどう表現するかということよりも、題材とか描かれるべき内容そのものが先に問われていいと思う。それがその作品の創作方法じたいを喚起してくる、あるいは作品を作る人たちが「問題」そのものに向き合って影響を与えられて、作品の方法論すらそこで生まれるぐらいにできないかなという、一つの実験性としての演劇をやっていいと思う。それは「ある特定のイデオロギーのためにはやらない」ということの手段でもあるんだけれど。
ただ、「日本の問題」っていう命題じたいが既に批評であり、同時に批評されるべきものなんじゃないかな。だって日本の問題じゃないじゃん。社会であり世界の問題じゃん、ほとんどのことが。「日本の」って切り出す時の一つの国家意識というかね、日本っていうアイデンティティーが、きちんとマイナスポイントでも自覚されているかどうか。「日本の問題」と言うことによって、さっき言った表現の所有格を解放したいということとはぜんぜん違う意味で、責任の所在が霧散するんですよ。ロマンティックに文学的に、「この時代の日本の人たちの問題でしたね」「はい、私もそう思います。私だけじゃないですからね」って、みんながしらを切れる。「こいつが悪いんだよ、責任取ってないんだよ」ってちゃんと言わなきゃ駄目なんだよ。そういうことに向かわないと、逆方向になる。あえて言えばね。「いや、そうじゃない。ちゃんとやるために必要な土壌を作るためにこのフェスティバルをやるんだ。大丈夫ですよ」って言ってほしいよね。具体論しかないんだよ、そうしないと思考停止する。フレームを設けることが表現だっていう誤解をしない方がいい。「日本の問題」って言って「お、何かな」って、そんなものはないよ。「問題」って言葉もジョークだって思ってやっているならいいけどね。日本でやられてる演劇とか小説、全部「日本の問題」って付けられるわけでさ。で、「日本の問題」を今年やって、来年どうするの? 「アメリカの問題」やる?
酒井 何かしら続けていく予定だって聞いていますが……。
坂手 一つの取っかかりとしてはいいわけ。でも予定調和に嵌っちゃうと危険だよね。被災の現実もそうだけど、ロマンティックに言わない方がいい、文学的に考えちゃうと非常に難しい。
酒井 具体的な問題として提示することでですか?
坂手 いや、演劇の持ってる一つの特性としては、ライブであることの良さでね。今まさに舞台にいる俳優が何かを感じていて、その感じている俳優を見てお客さんも彼がこう感じているんだと感じる。それを俳優も感じる。そういう相互作用だよね。井上ひさしさんもよく仰ってたけど、350人のお客さんが来ていても、他に2人観に来るか来ないかで芝居って変わるよ。だからこの場面でクスッと誰かが笑うだけで芝居が変わるってことはあるよ。そういうふうに芝居は作られているから。感じ方は人それぞれで、それを出すのも自由なんだけど、ただそこにあることを自明性として保守的に現状肯定してしまうと、それは消去法的に文学性と呼ばれてしまう。そうじゃなくて、誰とでも共有できる問題として語りながら、なおかつそれが己の表現になってるかどうかが表現者の腕力で、それができなきゃいけない。どんなオーケストラとやっても馴染めるし、同時に自分の個性も出せるというふうに、プレイヤーはいなきゃいけない。